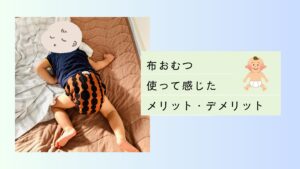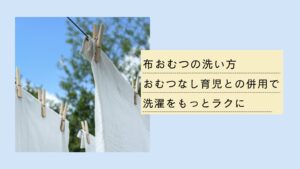布おむつ育児のその後 -支援級を選んだ我が家の就学Story
長男は現在、小学校2年生。
就学を前に、親としてたくさんの悩みや迷いがありました。
そんな中、布おむつ育児で自然と身についた「子ども軸」の視点
ネットの情報は参考程度にとどめ、「今、この子にとって何が最適か?」を基準に判断。
周りと比べて「できる・できない」で見るのではなく、「この子にはこれがあるから大丈夫」と、子どもの強みを信じる視点
これらが私の判断を支えてくれました。
今回は、就学にあたり「普通級 or 支援級、どっち?」というテーマで、我が家の選択についてお話しします。
長男は、1年生から情緒の支援級に通っています。
就学前、「普通級でも過ごせるかもしれないけれど、彼にとってどちらがいいのか…」と悩みました。
この記事では、長男の発達障がい・療育の経緯、そして最終的に支援級を選んだ理由をお伝えします。
目次
- 発達障害の診断を受けるまでの経緯
- 利用した療育サービス:保育所等訪問支援
- 就学にあたり支援級に決めた理由
1. 発達障害の診断を受けるまでの経緯
「育てにくさ」を感じ始めたのは、長男が3歳の頃。
次男との比較からそう感じたのかもしれません。
でも、「育てにくい」と思うのは、私自身のキャパの狭さではないか…という葛藤もありました。
さかのぼると、1歳半健診時点での発語は「どうぞ」の1語のみ
3歳半の集団健診では、視力検査も聴力検査も拒否。
検診会場から逃亡し、保健士さんと一緒に大捜索し、駐車場で発見…という事件もありました。
その後、保健士さんとの電話相談を経て、心理士の方に相談。
療育センターを受診し、年中の春に**自閉スペクトラム症(ASD)**の診断を受けました。
2. 利用した療育サービス:保育所等訪問支援
長男が受けた療育サービスは「保育所等訪問支援」でした。
これは、障がいや発達に特性のある子どもが、保育園や学校などの集団生活に適応できるよう、専門の支援員が施設を訪問して支援する制度です。
保育士さんへ、子どもとの関わり方のアドバイスもしてくれます。
ちなみに・・・診断を受けた際、個人療育をおすすめされました。
しかし、療育センターの雰囲気を長男が嫌がっていたこと
そんな場所に、定期的に連れていくことを考えたときの、私自身のストレス(絶対イライラして怒るのが分かっていた)
子どもに何と説明して、連れて行ったらいいかわからない(障がいを短所のように伝えたくなかった)、というのがネックになり、療育を先延ばしにしていました。
そんなとき、保育園の担任の先生に「保育所等訪問支援」を勧められ、年長の1年間、福祉サービスを受けることに。
新しい場所や人が不慣れな長男にとって、慣れた場所で支援を受けられることは、とてもありがたかったです。
また、家ではよくしゃべるのに、保育園ではほとんど話さないなど、環境による違いがあり・・・
保育園で本人が何で困っているのかわからない状態で、就学に関して判断材料がありませんでした。
訪問支援を通じて、保育園での様子を知ることができたのは、就学に向けて支援級か普通級かを考えるうえで非常に役立ちました。
支援員の方は、長男の困っている様子を見てもすぐに手を出さず、「どうしたらいいと思う?」と問いかけ、必要なときにそっと背中を押してくれました。
訪問後には写真付きの報告書もいただき、集団生活での様子がよくわかりました。
個人的には、保育所等訪問支援は「子どものため」だけでなく、周囲の大人が子どもの特性を理解するための支援でもあると感じています。
1つのできない行動を、小さなステップに分けて考え、どこがネックになっているのか、何を支援すれば一歩踏み出せるのか。それを丁寧に教えていただきました。
布おむつ育児で培った排せつを小さなステップに分けて考える感覚に似ていました。
「できない」の裏にある小さなステップを見る視点を育ててくれたのだと、今振り返って強く感じます。
3. 就学にあたり支援級に決めた理由
保育園の先生や就学相談の相談員の方からは、支援級を勧められていました。
ただ、何か根拠を持って決断したいという思いがありました。
決め手になったのは、年長の1月に小学校に見学へ行ったこと。
普通級と支援級の授業を見て、長男がどちらの環境で過ごしやすいかをイメージできたことで、支援級を選びました。
同じ内容の算数の授業を見学したのですが、
大人数の中で授業を受けるというのは、実に多くの刺激があるのだと改めて感じました。
前にいる先生の話を聞きながら、黒板を見て、手元のプリントに取り組み、さらに黒板の答えを確認する。
この一連の流れの中で、周囲のざわめきや動きも加わると、長男にとっては注意が散りやすい環境なのかもしれない、と実感しました。
最初は「子どもに決めてもらおう」と思っていましたが、子どもにとって、保育園しか知らない状態で小学校の環境を選ぶのは難しいですよね。
支援級を選んだのも、「1年生はとりあえず支援級でやってみよう」という気持ちでした。
布おむつ育児で培った「トライ&エラー」の思考が、ここでも活きました。
長男には、「1年生は支援級だけど、2年生になって、大人数のクラスだけがいいなら、それでもいいよ」と伝えていましたが、
1年生の秋頃に、「2年生も支援級のままがいい」と、自分で決められるようになっていました。
ここで少し、支援級の学びの様子をご紹介:気になる方は、▶をクリックしてご確認ください
※長男の通う情緒の支援級の場合です。ご参考までに
・在籍は支援級なので、朝登校して荷物を置くのは支援級
・勉強に関しては、国語と算数だけ支援級、音楽、生活科、体育、図工などは交流級(=普通級)で勉強しています。
(ここは子どもの得意・不得意によって、変わってくる)
・交流級にも机があり、交流級で受ける授業のときは、支援級から移動して受ける。
・教科書は、普通級と同じものを使って、同じ内容を勉強しています(視覚的に補助するなど、教え方が変わる)
・自立学習という科目が、支援級にはあります
→内容はレクリエーションなど、遊びの中で学ぶ工夫がされているようです。
本人曰く「一番好きな授業」とのこと。
・クラスのメンバーが、学年ごっちゃ
→長男のクラスは、1年生1人、2年生3人(長男含む)、4年生1人、5年生1人の6人学級
・支援級同士で交流があり、支援級合同で給食を食べています。
今では、学校での出来事をとても楽しそうに話してくれます。
支援級には裏紙がたくさん用意されていて、絵を描くのが大好きな長男にとっては、まるで“創作の宝庫”
心地よい居場所になっているようです。
また、長男の描いた絵を「上手だね」と褒めてくれる友達が、支援級・交流級を問わずたくさんいて、その言葉が本人の大きな自信につながっています。
(画家になる!と言っています)
ちなみに、絵の上達は年長の頃に突然訪れました。
自分の「得意だと思える何か」を持って小学校に進学できたことは、長男にとって大きな支えになったと思います。
そのきっかけをくれた保育園の先生方には、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。
まとめ
布おむつ育児がくれた3つの視点
長男の就学にあたり、「普通級か支援級か」という選択に迷いながらも、布おむつ育児で自然と身についた視点が、親としての判断を支えてくれました。
①「子ども軸」で考える力
布おむつ育児では、排せつのタイミングや子どもの様子を観察しながら対応する日々の中で、「今、この子にとってどうするのが最適か?」という視点が育まれました。
この感覚が、就学の場面でも「周りと比べてどうか」ではなく、「この子にとってどちらが心地よく、安心して過ごせるか」を軸に判断する力につながりました。
②「できない」の裏にあるステップを見る力
布おむつ育児では、排せつの習得を小さなステップに分けて考える必要がありました。
この経験が、療育の場面でも活き、「できない行動」の背景にある“つまずきポイント”を丁寧に見つける力・理解する力に繋がりました。
③「トライ&エラー」を恐れない柔軟さ
布おむつ育児は、試してみて、失敗して、また工夫する…の繰り返し。
この「トライ&エラー」の思考が、就学の選択にも活かされました。
「まずは支援級で試してみよう」「合わなければ変えてもいい」という柔軟な姿勢が、長男自身が安心して選択できる土台になりました。
結果的に、2年生も支援級を選んだのは、本人の意思によるものでした。
これからも、きっと悩みは続いていくと思います。
中学、高校、大学…進学先や進路の選択肢は広がり、迷う場面も増えていくでしょう。
彼が「どんな道を進みたいか」を考えるとき、自分の特性を理解したうえで選択できるようにしてあげたい。
たとえば、「苦手だけど挑戦したい」のか、「得意を活かせる環境を選びたい」のか——その判断材料を、今のうちから少しずつ積み重ねていけたらと思っています。
そのためにも、得意を伸ばすことや、「わかった!」「できた!」という成功体験を通じて、
「自分は何が得意で、何が苦手なのか=自分の特性」を、子ども時代のうちに少しずつ理解していけるよう、サポートしていきたいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!